Extracurricular Activity
課外活動
 Hello, Jonathan the camera man here. Today I would like to introduce the special workshops we held here at ICT Hakusanroku campus. Students have their final exams in the end of January. However, they do not go home for another month. What do they do? During the month of February, students participate in various activities and workshops. Some of these workshops are held by special teachers we invited from various fields of the business world. Here are a peek into what we did this year. For last year's workshops, check the journal entry here.
Hello, Jonathan the camera man here. Today I would like to introduce the special workshops we held here at ICT Hakusanroku campus. Students have their final exams in the end of January. However, they do not go home for another month. What do they do? During the month of February, students participate in various activities and workshops. Some of these workshops are held by special teachers we invited from various fields of the business world. Here are a peek into what we did this year. For last year's workshops, check the journal entry here.
こんにちは、ジョナサンです。国際高専の白山麓キャンパスでは、授業が終わった2月に特別講師による課外活動が行われます。
PR Video Editing Workshop Using Adobe Ai and Premiere (Feb.7)
The first workshop was the "PR Video Editing Workshop Using Adobe Ai and Premiere" conducted by Mamoru Yoshida of Yoshita Design Planning Co. In this workshop, students were divided into groups of three and given the task of creating an ICT promotion video. They also created a logo for their team and a thumbnail for their video. Yoshida-san showed several examples and methods to create effective images and explained that dividing the workload among the team members was key. Below are the results of each group. During reflection, Yoshida-san said "ICT students had a unique point of view and I learned a lot. I hope that you tackle each obstacle from multiple angles and use teamwork. Seeing other people's ideas is always worthwhile."
2月7日(金)、「Adobe Ai及びPremiereを活用したPR動画作成ワークショック」が(株)ヨシタデザインプランニング代表取締役 葭田護氏の指導のもと行われました。この活動では、学生がグループに分かれて国際高専のプロモーションビデオを制作しました。終了後、葭田氏は「国際高専の学生は発想が独特で勉強になった。これからもチームで協力して課題に取り組んで欲しい」と語りました。
Lecture about studying abroad (Feb.8)
On February 8 (Sat), students listened to a lecture by Gen Ueda, a graduate of ICT from 2011. Ueda-san participated in most of the oversea programs including a year in New Zealand. Following his passion, he created the company ENGLISH CORES (English Consulting & Resources) and helped many Japanese students study abroad in the United States. In the lecture, Ueda-san spoke about his experience with helping students studying aboard, and gave advice based on what he had learned.
The story he told was of a high school student that homestayed in the United States. After a while, the student called Ueda-san saying that his elderly homestay parents did not talk much or take him out on the weekends. It turned out that the student's family normally went out together every weekend and therefore the student felt robbed of this entertainment. Hearing the student's complaint, Ueda-san gave him the advice to talk to the homestay parents and find out what they are interested in. It turned out that the father was a sports enthusiast and they began to watch games together on TV and go out to stadiums on the weekends.
The moral of the story is that every homestay student Ueda-san has setup always encounters some form of distress sooner or later. However, instead of falling into depression or giving up, it is important to "find positive aspects of what you think is a negative situation." Ueda-san explained this as having a "Plan B".
The second and third pieces of advice Ueda-san gave the students was from his personal experience studying English in school. The first he titled "I CAN AND I WILL". This was a reminder that you need to put effort into something if you want to achieve a high goal. "Effort may not always pay off. However, successful people are always the ones that put in the effort" he explained. He also warned the students about overdoing it. Ueda-san spent a lot of time studying English in his student years, which sometimes lead to him burning out. He recommended finding a hobby or something enjoying to do to avoid this.
The final piece of advice was to help each other. Ueda-san observed many examples of students who are trying hard being pulled down by other students who did not take a liking to their effort. He emphasized the importance for supporting each other for a better future, not only for oneself by also for mankind.
2月8日(土)、国際高専を2011年に卒業した上田源氏が「英語学習と海外でのキャリアについて」と題して講習を行いました。上田氏は卒業後、海外留学コンサルティングや英会話教室を行うENGLISH CORESを設立、講習ではニュージーランド留学前の後輩に対して体験談をもとにアドバイスを送りました。「ホームステイをすると必ず不満が出てくる。しかし、人生はネガティブの状況からポジティブ要素を見つけることが大事だ」と語りました。さらに上田氏はライブラリーセンターに籠って猛烈に勉強していた学生時代を振り返り、「高い目標を達成したければ継続力が必要だ」「努力が実るとは限らないが、成功している人は少なからず努力している」と述べました。しかし、反対に自身の経験から燃え尽きることを避けるために趣味の時間の大切さにも触れました。また最後に、卒業してからも協力し合える仲間でいて欲しいと訴えかけました。
SDGs Lecture and JICA Report (Feb.13)
On February 13 (Thu), Students listened to a lecture by Kanazawa Institute of Technology (KIT) professor Yasuhide Suzuki, Satoshi Kato, and JICA oversea volunteer Kazuha Tamba. KIT is conducting a project to create a sustainable source of oil from Jatropha plants in Mozambique. You can read more about the project here. Professor Suzuki explained the history of the oil crisis in the 1970's and how various resources became more valuable. The Jatropha project aims to turn deserts into Jatropha fields, which they can harvest and create oil. The merits are that Jatropha will not damage the environment since the land it grows on is starting out as a desert. Other plants are quickly eaten by roaming animals. However, Jatropha is poisonous so it is left to grow. Currently they are researching how to efficiently remove the toxin, produce fuel, and sustain the business with local workers.
 Next, professor Kato introduced the Mozambique culture and his experience there. Mozambique is a small country east of South Africa. The KIT group built a shop to sell the fuel they created from the Jatropha plants and generators that use it to create electricity. The village where this shop is located has no electricity so people are dependent on such generators to use electronic devices such as cell phones. Professor Kato explained how they developed an affordable lease system to adapt to the needs of the local people.
Next, professor Kato introduced the Mozambique culture and his experience there. Mozambique is a small country east of South Africa. The KIT group built a shop to sell the fuel they created from the Jatropha plants and generators that use it to create electricity. The village where this shop is located has no electricity so people are dependent on such generators to use electronic devices such as cell phones. Professor Kato explained how they developed an affordable lease system to adapt to the needs of the local people.
The final speaker, Kazuha Tanzawa served as a volunteer for one year in the Jangamo district of Mozambique helping the local people starting new businesses and farms. Kazuha-san explained that the people of Mozambique are very kind but also lazier compared to people in Japan and take a lot of coaxing. Projects she started or helped out with include several farms, the making and selling of soap, beeswax cream and honey, and a general store.
Kazuha-san continued to share some of her hardships. When Kazuha-san introduced herself to the local people as a volunteer, many of them expected she would simply give them money. It was difficult for her to explain that she wanted to help them in a sustainable way. Most of the local people were unfamiliar with farming and needed a lot of coaching. Also, language and cultural differences, such as the Mozambique people's belief in witchcraft were matters that needed special attention.
In return, volunteer work is a good opportunity to experience starting a business with limited money. Also, it felt great when the projects took off successfully and the local people could sustain them. Kazuha-san recommended applying for an oversea volunteer as there is always something you can do and the experience is worth it.
2月13日(木)、金沢工業大学の加藤聰先生と鈴木康允先生による「モザンビークの無電化村におけるジャトロファバイオ燃料を活かした小規模電化プロジェクト」とJICA海外協力隊の丹澤一葉氏によるボラインティア体験についての報告が行われました。ジャトロファの植物はバイオ燃料の原料となり、エネルギー問題の解決策として期待されています。金沢工業大学は東京大学、久留米大学、日本植物燃料、アフリカ開発協会、モザンビークのエドワルド・モンドラーネ大学と協同してモザンビークの砂漠地帯にジャトロファの栽培と継続的にバイオディーゼル燃料を作る試みを続けています。通常砂漠を農地化しようとすると野生動物に食べられてしまいますが、ジャトロファは毒素を持っているため食べられません。収穫したジャトロファは現地の施設でバイオ燃料に変えて、発電機と一緒に販売しています。加藤先生は現地を視察して住民のニーズに合わせて技術者を育てたり、リースシステムを導入した体験について話しました。
丹澤一葉氏は2018年にモザンビークへ一年間のJICA海外協力隊として、現地住民と一緒に事業を起こしたり、畑を作ったり、お店を開いたりするなどのボランティア活動を行いました。丹澤氏は苦労した点として「ボランティアだと伝えるとお金がもらえると思われることが多い、理解してもらうことが大変」「モザンビーク人は優しいが、のんびりした人が多い、指導しないと動かない」「黒魔術や女性に対する価値観など、日本との文化の差がある」と振り返りました。逆に得たものとして「少額のお金でビジネスを起こす経験」「事業が軌道に乗った時の達成感」「他ではできない体験」を挙げ、参加を勧めました。
Performing Arts Workshop (Feb.18)
On, February 18 (Tue), we held a Performing Arts special session in the Maker Studio 3 area in front of the big staircase. Daikoku-sensei, our Performing Arts teacher and jazz singer invited two professional musicians for this special occasion. Chirori is the leader of the Beat Box Academy, and a beatboxer himself. He hosts the "BeatBoxBattle", the first beatbox tournament in the Hokuriku region, performs regularly, and opens workshops for kids, old people's homes, and on television. Yuhi Taka is professional pianist who both performs and writes. His style is unique with its foundation in jazz, adding elements from all sorts of music genres. After apprenticing to renowned pianists such as Takashi Mizoguchi from age fourteen and Hiroshi Tanaka from age twenty, he began his carrier as a university student.
During this special workshop, the first and second-year students listened to solo and collaborative sessions by Uozumi-sensei, Chirori-san, and Yuhi-san. Afterwards, they each received an instrument and we held a grand finale concert together. Most of the students were shy and needed some coaxing, but began to enjoy themselves as soon as the session began. Here are some pictures of the one and only "ICT Band".
2月18日(火)、パフォーミング・アーツの特別活動として「ビートボックス&演奏実習」が行われました。特別講師として普段学生たちを教えている大黒友理先生に加えてBeatBoxAcademy代表のちrori氏、フリーランスのピアニストの高雄飛氏をゲストに呼びました。ちrori氏は北陸初となるBeatBoxBattle大会を主催した富山県を代表するヒューマン・ビート・ボクサーです。また、テレビ、ラジオ、教育現場や福祉施設などでワークショップを開いています。高雄飛氏は金沢を代表するピアニスト溝口尚氏や世界的ピアニスト田中裕士氏に師事するなど、若い時から演奏活動を始め、ジャズを土台にあらゆる音楽を取り込んだ独特のスタイルで演奏、作曲、編曲を行っています。現在は演奏活動、福祉施設での音楽教室、CMへの楽曲提供などをしています。学生たちは演奏家たちの奏でる音楽を聴いたのち、それぞれ楽器を持って講師たちの指導のもとセッションを楽しみました。
Future Insight & Design Library Workshop (Feb.21)
The workshop on February 21 (Fri) was "Future Insight & Design Library Workshop" led by Naoki Yamamoto of Kawai-jyuku. Yamamoto-san is a specialist of books and libraries. He works for the Future Research Program at Kawai-jyuku, writes monthly articles on the book review website "HONZ", and is a designer of libraries and bookshelves.
First, Yamamoto-san gave a lecture about the history and current state of books in Japan. Books have lost their popularity due to the accessibility of the internet. Less and less books are selling and books stores are going out of business all over the country. Yamamoto-san lamented this movement. However, he also described it as an opportunity for innovation. Writers and publishers are finding clever ways to sell books such as designing new book covers by famous artists, and opening bookstores with stylish cafes.
When asked if they used the Hakusanroku library regularly, none of the students raised their hands (much to the grief of the teachers in the room). Yamamoto-san explained that ICT had a wonderful library and asked the students to go and find three books they had never read before. After their exploration of the library, students returned with several interesting books each. They showed their findings to each other and talked amongst themselves.
The next task was to design new methods to draw people and books together. Each group began brainstorming and designing a new service using the format provided by Yamamoto-san, which they gave presentations about at the end of the workshop. After the students had left, Yamamoto-san remarked that he was pleasantly surprised with ICT students' creativity and their experience with the design process.
2月21日(金)、「Future Insight & Design Workshop」と題して河合塾未来研究プログラムの山本尚毅氏による特別活動が行われました。山本氏は河合塾のプログラム開発担当として人材育成に努める他、本のスペシャリストとしておすすめ本を紹介するサイト「HONZ」で数多くの書評を行っています。このワークショップでは、まず日本における本の歴史と現状について説明しました。現在、インターネットを通じて情報が入手しやすくなって本の需要が落ちています。その結果、年々閉店する本屋が増えています。山本氏はこの現状を嘆きながらも、生き残るために、表紙を有名なイラストレーターの絵に変えたり、おしゃれなカフェを設置した本屋など、クリエイティブな手法もたくさん生まれていると伝えました。
「白山麓キャンパスの図書館を使っていますか?」と聞かれると、学生の手は上がりませんでした。山本氏は続けて「白山麓キャンパスの図書館は素晴らしい。とてもこだわって本を選んでいる」「これから普段手に取らないような本を3冊取ってきてください」と指示しました。戻ってきた学生たちは自分の興味に合わせて選んだ本をお互いに見せ合って話していました。
ワークショップの後半は「どうやったら、人と本の関係をもっと身近にすることができるだろうか?」というテーマでデザイン活動が行われました。学生たちは山本氏が用意した形式にとってブレインストーミングし、グループで発表しました。終了後、山本氏に話を聞くと「こういうワークショップは普通デザイン活動を理解するために時間がかかってしまうが、国際高専の学生はものづくりに慣れていた。また、アイデアがどんどん出てきて驚いた」と振り返りました。
Branding Workshop by DMM.com (Feb. 25)
The last workshop was titled "Branding Workshop" by Yurie Maruyama from DMM.com. Yurie Maruyama is a graduate of ICT and one of the first students to join the one year program at Otago Polytechnic in New Zealand. In this workshop, students were divided into groups and given the task of creating a catchphrase for the ICT open campus. Maruyama-san explained the importance of developing a "concept", especially when working with other. A concept is an idea or direction when creating something new. Different people have different images of words such as "cool" or "cute". Therefore, at DMM.com, teams create a cluster of pictures that match the concept so that all team members share the same image. Also, Maruyama-san emphasized the importance to create a customer persona in order to have a clear picture of who the product is aimed for. Students used the methods Maruyama-san uses in her work and gave a presentation of their results at the end.
2月25日(火)に行われた最後の特別活動は2008年に国際高専を卒業したDMM.com企画開発部の丸山祐里恵氏による「ブランディング・ワークショップ」でした。このワークショップでは学生がグループに分かれて国際高専の学校見学会のキャッチコピーを作りました。丸山氏は「複数人でものづくりを行う場合は「コンセプト」を決めることが重要です。『かわいい』『かっこいい』は人によってイメージが違うので、全員が同じ感覚を持たないとチグハグになってしまう」と説明しました。このイメージを統一するためにコンセプトと合った複数の画像を並べたムードボードを制作する方法や、商品のターゲットとなる顧客に狙いを澄ますためにユーザーペルソナを作ることを学びました。これらの手法は丸山氏がDMM.comの企画開発で実際に使っている生きた技術です。
Conclusion
I enjoy this final month perhaps more than any other in the school year. Students are learning different things, using their free time to work on personal projects, and winding down for the end of the year. This year's extracurricular classes were unique, educational, and a good opportunity for students to notice their growth over the year. It is also a chance for first and second year students to work together. This is something I believe we need more of in the future. Thanks for reading this long report, see you all again next year.
Jonathan
2月に行われた特別活動はバリエーションにとんでおり、教育的効果に加えて学生たちが1年間培ってきた能力を発揮する場として効果的だったと思います。また、1年生と2年生が一緒に学ぶ機会も少ないので、良い刺激になったと感じました。
大脇 ジョナサン・幸介
 Hello, Jonathan the camera man here. Today I would like to introduce the special workshops we held here at ICT Hakusanroku campus. Students have their final exams in the end of January. However, they do not go home for another month. What do they do? During the month of February, students participate in various activities and workshops. Some of these workshops are held by special teachers we invited from various fields of the business world. Here are a peek into what we did this year. For last year's workshops, check the journal entry here.
Hello, Jonathan the camera man here. Today I would like to introduce the special workshops we held here at ICT Hakusanroku campus. Students have their final exams in the end of January. However, they do not go home for another month. What do they do? During the month of February, students participate in various activities and workshops. Some of these workshops are held by special teachers we invited from various fields of the business world. Here are a peek into what we did this year. For last year's workshops, check the journal entry here.
こんにちは、ジョナサンです。国際高専の白山麓キャンパスでは、授業が終わった2月に特別講師による課外活動が行われます。
PR Video Editing Workshop Using Adobe Ai and Premiere (Feb.7)
The first workshop was the "PR Video Editing Workshop Using Adobe Ai and Premiere" conducted by Mamoru Yoshida of Yoshita Design Planning Co. In this workshop, students were divided into groups of three and given the task of creating an ICT promotion video. They also created a logo for their team and a thumbnail for their video. Yoshida-san showed several examples and methods to create effective images and explained that dividing the workload among the team members was key. Below are the results of each group. During reflection, Yoshida-san said "ICT students had a unique point of view and I learned a lot. I hope that you tackle each obstacle from multiple angles and use teamwork. Seeing other people's ideas is always worthwhile."
2月7日(金)、「Adobe Ai及びPremiereを活用したPR動画作成ワークショック」が(株)ヨシタデザインプランニング代表取締役 葭田護氏の指導のもと行われました。この活動では、学生がグループに分かれて国際高専のプロモーションビデオを制作しました。終了後、葭田氏は「国際高専の学生は発想が独特で勉強になった。これからもチームで協力して課題に取り組んで欲しい」と語りました。
Lecture about studying abroad (Feb.8)
On February 8 (Sat), students listened to a lecture by Gen Ueda, a graduate of ICT from 2011. Ueda-san participated in most of the oversea programs including a year in New Zealand. Following his passion, he created the company ENGLISH CORES (English Consulting & Resources) and helped many Japanese students study abroad in the United States. In the lecture, Ueda-san spoke about his experience with helping students studying aboard, and gave advice based on what he had learned.
The story he told was of a high school student that homestayed in the United States. After a while, the student called Ueda-san saying that his elderly homestay parents did not talk much or take him out on the weekends. It turned out that the student's family normally went out together every weekend and therefore the student felt robbed of this entertainment. Hearing the student's complaint, Ueda-san gave him the advice to talk to the homestay parents and find out what they are interested in. It turned out that the father was a sports enthusiast and they began to watch games together on TV and go out to stadiums on the weekends.
The moral of the story is that every homestay student Ueda-san has setup always encounters some form of distress sooner or later. However, instead of falling into depression or giving up, it is important to "find positive aspects of what you think is a negative situation." Ueda-san explained this as having a "Plan B".
The second and third pieces of advice Ueda-san gave the students was from his personal experience studying English in school. The first he titled "I CAN AND I WILL". This was a reminder that you need to put effort into something if you want to achieve a high goal. "Effort may not always pay off. However, successful people are always the ones that put in the effort" he explained. He also warned the students about overdoing it. Ueda-san spent a lot of time studying English in his student years, which sometimes lead to him burning out. He recommended finding a hobby or something enjoying to do to avoid this.
The final piece of advice was to help each other. Ueda-san observed many examples of students who are trying hard being pulled down by other students who did not take a liking to their effort. He emphasized the importance for supporting each other for a better future, not only for oneself by also for mankind.
2月8日(土)、国際高専を2011年に卒業した上田源氏が「英語学習と海外でのキャリアについて」と題して講習を行いました。上田氏は卒業後、海外留学コンサルティングや英会話教室を行うENGLISH CORESを設立、講習ではニュージーランド留学前の後輩に対して体験談をもとにアドバイスを送りました。「ホームステイをすると必ず不満が出てくる。しかし、人生はネガティブの状況からポジティブ要素を見つけることが大事だ」と語りました。さらに上田氏はライブラリーセンターに籠って猛烈に勉強していた学生時代を振り返り、「高い目標を達成したければ継続力が必要だ」「努力が実るとは限らないが、成功している人は少なからず努力している」と述べました。しかし、反対に自身の経験から燃え尽きることを避けるために趣味の時間の大切さにも触れました。また最後に、卒業してからも協力し合える仲間でいて欲しいと訴えかけました。
SDGs Lecture and JICA Report (Feb.13)
On February 13 (Thu), Students listened to a lecture by Kanazawa Institute of Technology (KIT) professor Yasuhide Suzuki, Satoshi Kato, and JICA oversea volunteer Kazuha Tamba. KIT is conducting a project to create a sustainable source of oil from Jatropha plants in Mozambique. You can read more about the project here. Professor Suzuki explained the history of the oil crisis in the 1970's and how various resources became more valuable. The Jatropha project aims to turn deserts into Jatropha fields, which they can harvest and create oil. The merits are that Jatropha will not damage the environment since the land it grows on is starting out as a desert. Other plants are quickly eaten by roaming animals. However, Jatropha is poisonous so it is left to grow. Currently they are researching how to efficiently remove the toxin, produce fuel, and sustain the business with local workers.
 Next, professor Kato introduced the Mozambique culture and his experience there. Mozambique is a small country east of South Africa. The KIT group built a shop to sell the fuel they created from the Jatropha plants and generators that use it to create electricity. The village where this shop is located has no electricity so people are dependent on such generators to use electronic devices such as cell phones. Professor Kato explained how they developed an affordable lease system to adapt to the needs of the local people.
Next, professor Kato introduced the Mozambique culture and his experience there. Mozambique is a small country east of South Africa. The KIT group built a shop to sell the fuel they created from the Jatropha plants and generators that use it to create electricity. The village where this shop is located has no electricity so people are dependent on such generators to use electronic devices such as cell phones. Professor Kato explained how they developed an affordable lease system to adapt to the needs of the local people.
The final speaker, Kazuha Tanzawa served as a volunteer for one year in the Jangamo district of Mozambique helping the local people starting new businesses and farms. Kazuha-san explained that the people of Mozambique are very kind but also lazier compared to people in Japan and take a lot of coaxing. Projects she started or helped out with include several farms, the making and selling of soap, beeswax cream and honey, and a general store.
Kazuha-san continued to share some of her hardships. When Kazuha-san introduced herself to the local people as a volunteer, many of them expected she would simply give them money. It was difficult for her to explain that she wanted to help them in a sustainable way. Most of the local people were unfamiliar with farming and needed a lot of coaching. Also, language and cultural differences, such as the Mozambique people's belief in witchcraft were matters that needed special attention.
In return, volunteer work is a good opportunity to experience starting a business with limited money. Also, it felt great when the projects took off successfully and the local people could sustain them. Kazuha-san recommended applying for an oversea volunteer as there is always something you can do and the experience is worth it.
2月13日(木)、金沢工業大学の加藤聰先生と鈴木康允先生による「モザンビークの無電化村におけるジャトロファバイオ燃料を活かした小規模電化プロジェクト」とJICA海外協力隊の丹澤一葉氏によるボラインティア体験についての報告が行われました。ジャトロファの植物はバイオ燃料の原料となり、エネルギー問題の解決策として期待されています。金沢工業大学は東京大学、久留米大学、日本植物燃料、アフリカ開発協会、モザンビークのエドワルド・モンドラーネ大学と協同してモザンビークの砂漠地帯にジャトロファの栽培と継続的にバイオディーゼル燃料を作る試みを続けています。通常砂漠を農地化しようとすると野生動物に食べられてしまいますが、ジャトロファは毒素を持っているため食べられません。収穫したジャトロファは現地の施設でバイオ燃料に変えて、発電機と一緒に販売しています。加藤先生は現地を視察して住民のニーズに合わせて技術者を育てたり、リースシステムを導入した体験について話しました。
丹澤一葉氏は2018年にモザンビークへ一年間のJICA海外協力隊として、現地住民と一緒に事業を起こしたり、畑を作ったり、お店を開いたりするなどのボランティア活動を行いました。丹澤氏は苦労した点として「ボランティアだと伝えるとお金がもらえると思われることが多い、理解してもらうことが大変」「モザンビーク人は優しいが、のんびりした人が多い、指導しないと動かない」「黒魔術や女性に対する価値観など、日本との文化の差がある」と振り返りました。逆に得たものとして「少額のお金でビジネスを起こす経験」「事業が軌道に乗った時の達成感」「他ではできない体験」を挙げ、参加を勧めました。
Performing Arts Workshop (Feb.18)
On, February 18 (Tue), we held a Performing Arts special session in the Maker Studio 3 area in front of the big staircase. Daikoku-sensei, our Performing Arts teacher and jazz singer invited two professional musicians for this special occasion. Chirori is the leader of the Beat Box Academy, and a beatboxer himself. He hosts the "BeatBoxBattle", the first beatbox tournament in the Hokuriku region, performs regularly, and opens workshops for kids, old people's homes, and on television. Yuhi Taka is professional pianist who both performs and writes. His style is unique with its foundation in jazz, adding elements from all sorts of music genres. After apprenticing to renowned pianists such as Takashi Mizoguchi from age fourteen and Hiroshi Tanaka from age twenty, he began his carrier as a university student.
During this special workshop, the first and second-year students listened to solo and collaborative sessions by Uozumi-sensei, Chirori-san, and Yuhi-san. Afterwards, they each received an instrument and we held a grand finale concert together. Most of the students were shy and needed some coaxing, but began to enjoy themselves as soon as the session began. Here are some pictures of the one and only "ICT Band".
2月18日(火)、パフォーミング・アーツの特別活動として「ビートボックス&演奏実習」が行われました。特別講師として普段学生たちを教えている大黒友理先生に加えてBeatBoxAcademy代表のちrori氏、フリーランスのピアニストの高雄飛氏をゲストに呼びました。ちrori氏は北陸初となるBeatBoxBattle大会を主催した富山県を代表するヒューマン・ビート・ボクサーです。また、テレビ、ラジオ、教育現場や福祉施設などでワークショップを開いています。高雄飛氏は金沢を代表するピアニスト溝口尚氏や世界的ピアニスト田中裕士氏に師事するなど、若い時から演奏活動を始め、ジャズを土台にあらゆる音楽を取り込んだ独特のスタイルで演奏、作曲、編曲を行っています。現在は演奏活動、福祉施設での音楽教室、CMへの楽曲提供などをしています。学生たちは演奏家たちの奏でる音楽を聴いたのち、それぞれ楽器を持って講師たちの指導のもとセッションを楽しみました。
Future Insight & Design Library Workshop (Feb.21)
The workshop on February 21 (Fri) was "Future Insight & Design Library Workshop" led by Naoki Yamamoto of Kawai-jyuku. Yamamoto-san is a specialist of books and libraries. He works for the Future Research Program at Kawai-jyuku, writes monthly articles on the book review website "HONZ", and is a designer of libraries and bookshelves.
First, Yamamoto-san gave a lecture about the history and current state of books in Japan. Books have lost their popularity due to the accessibility of the internet. Less and less books are selling and books stores are going out of business all over the country. Yamamoto-san lamented this movement. However, he also described it as an opportunity for innovation. Writers and publishers are finding clever ways to sell books such as designing new book covers by famous artists, and opening bookstores with stylish cafes.
When asked if they used the Hakusanroku library regularly, none of the students raised their hands (much to the grief of the teachers in the room). Yamamoto-san explained that ICT had a wonderful library and asked the students to go and find three books they had never read before. After their exploration of the library, students returned with several interesting books each. They showed their findings to each other and talked amongst themselves.
The next task was to design new methods to draw people and books together. Each group began brainstorming and designing a new service using the format provided by Yamamoto-san, which they gave presentations about at the end of the workshop. After the students had left, Yamamoto-san remarked that he was pleasantly surprised with ICT students' creativity and their experience with the design process.
2月21日(金)、「Future Insight & Design Workshop」と題して河合塾未来研究プログラムの山本尚毅氏による特別活動が行われました。山本氏は河合塾のプログラム開発担当として人材育成に努める他、本のスペシャリストとしておすすめ本を紹介するサイト「HONZ」で数多くの書評を行っています。このワークショップでは、まず日本における本の歴史と現状について説明しました。現在、インターネットを通じて情報が入手しやすくなって本の需要が落ちています。その結果、年々閉店する本屋が増えています。山本氏はこの現状を嘆きながらも、生き残るために、表紙を有名なイラストレーターの絵に変えたり、おしゃれなカフェを設置した本屋など、クリエイティブな手法もたくさん生まれていると伝えました。
「白山麓キャンパスの図書館を使っていますか?」と聞かれると、学生の手は上がりませんでした。山本氏は続けて「白山麓キャンパスの図書館は素晴らしい。とてもこだわって本を選んでいる」「これから普段手に取らないような本を3冊取ってきてください」と指示しました。戻ってきた学生たちは自分の興味に合わせて選んだ本をお互いに見せ合って話していました。
ワークショップの後半は「どうやったら、人と本の関係をもっと身近にすることができるだろうか?」というテーマでデザイン活動が行われました。学生たちは山本氏が用意した形式にとってブレインストーミングし、グループで発表しました。終了後、山本氏に話を聞くと「こういうワークショップは普通デザイン活動を理解するために時間がかかってしまうが、国際高専の学生はものづくりに慣れていた。また、アイデアがどんどん出てきて驚いた」と振り返りました。
Branding Workshop by DMM.com (Feb. 25)
The last workshop was titled "Branding Workshop" by Yurie Maruyama from DMM.com. Yurie Maruyama is a graduate of ICT and one of the first students to join the one year program at Otago Polytechnic in New Zealand. In this workshop, students were divided into groups and given the task of creating a catchphrase for the ICT open campus. Maruyama-san explained the importance of developing a "concept", especially when working with other. A concept is an idea or direction when creating something new. Different people have different images of words such as "cool" or "cute". Therefore, at DMM.com, teams create a cluster of pictures that match the concept so that all team members share the same image. Also, Maruyama-san emphasized the importance to create a customer persona in order to have a clear picture of who the product is aimed for. Students used the methods Maruyama-san uses in her work and gave a presentation of their results at the end.
2月25日(火)に行われた最後の特別活動は2008年に国際高専を卒業したDMM.com企画開発部の丸山祐里恵氏による「ブランディング・ワークショップ」でした。このワークショップでは学生がグループに分かれて国際高専の学校見学会のキャッチコピーを作りました。丸山氏は「複数人でものづくりを行う場合は「コンセプト」を決めることが重要です。『かわいい』『かっこいい』は人によってイメージが違うので、全員が同じ感覚を持たないとチグハグになってしまう」と説明しました。このイメージを統一するためにコンセプトと合った複数の画像を並べたムードボードを制作する方法や、商品のターゲットとなる顧客に狙いを澄ますためにユーザーペルソナを作ることを学びました。これらの手法は丸山氏がDMM.comの企画開発で実際に使っている生きた技術です。
Conclusion
I enjoy this final month perhaps more than any other in the school year. Students are learning different things, using their free time to work on personal projects, and winding down for the end of the year. This year's extracurricular classes were unique, educational, and a good opportunity for students to notice their growth over the year. It is also a chance for first and second year students to work together. This is something I believe we need more of in the future. Thanks for reading this long report, see you all again next year.
Jonathan
2月に行われた特別活動はバリエーションにとんでおり、教育的効果に加えて学生たちが1年間培ってきた能力を発揮する場として効果的だったと思います。また、1年生と2年生が一緒に学ぶ機会も少ないので、良い刺激になったと感じました。
大脇 ジョナサン・幸介
 皆さん、こんにちは。S科2年の鷺島です。今回は私が参加した、プロコンとロボコンに並ぶ高専三大コンテストの一つ、デザインコンペティション(以下デザコン)について書いていきます。
皆さん、こんにちは。S科2年の鷺島です。今回は私が参加した、プロコンとロボコンに並ぶ高専三大コンテストの一つ、デザインコンペティション(以下デザコン)について書いていきます。
デザコンは幾つかの区分に分かれていますが、私たち白山麓キャンパスの学生が参加できるのは、プレデザコン(高専1から3年生対象)となります。プレデザコンと言っても、分野が空間デザインフィールド(建築の透視図)、創造デザインフィールド(ロゴデザイン)、A Mデザインフィールド(3Dプリント)の3つに分かれており、それぞれの学生の得意分野で取り組むことができます。私自身は創造デザインフィールドを選択して今年の東京大会に参加しました。
今回のテーマは「名取市において、自然がもたらした試練を乗り越える力となった人と人とつながりを、次代へと継承してゆくこと」で、これを題材にしたロゴを作成しました。ここからは、簡単に何を経て完成へと至ったのか書いていきたいと思います。まず最初にしたのはテーマの咀嚼です。とくに今回のテーマは複雑で、最終的には「震災を乗り越えた人のつながりを示す」という一文に縮めました。次がアイデア出し、続いてブラッシュアップに入ります。ここが一番時間がかかる工程で、それぞれ1週間以上かかります。特にブラッシュアップに関しては、1つのロゴの些細な表現の差異を比べながら作業していくので、かなり疲れました。最後に提出資料にまとめれば完成です。どんどんアイデアが形になっていき、最終的に想像以上の作品が完成するのはとても壮観です。この活動を通して、アイデア創出の楽しさを再確認することができました。結果としては特別賞(審査委員会から頂ける賞)を獲得することができて嬉しく思います。
この分野は、アイデア勝負の部分も多く、サポートして頂ける先生たちも付いているので、初心者でも気軽に始められます。気になる人は是非最初の一歩を国際高専で踏み出してみてください。
S科2年 鷺島悠人
Hello everyone. My name is Sagishima and I am a second-year student of the department of science and technology. Today I would like to write about the Kosen Design Competition (DezaCon), which I participated in and is counted as one of the three big Kosen Contests along with the ProCon and RoboCon.
The DezaCon is divided into several divisions. The division that students from the Hakusanroku campus can participate in is the Pre-DezaCon (first- to third-year students). This Pre-DezaCon is further divided into three fields: the Space Design Field (architectural perspective drawing), Creative Design Field (logo design), and AM Design Field. (3D printing) Students can choose which fields they wish to compete in. I selected the Creative Design Field and entered this year's Tokyo tournament.
This year's theme was to create a logo based on the concept "Passing down the bond between people of Natori city who overcame the trial of nature." I would like to briefly describe how I reached my final product. First, I broke down the theme. This year's theme was complex, so I simplified it to the sentence "Display the bond between people who overcame the earthquake." Next, I brainstormed and began the brushing up process. These took the longest amount of time; about one week for each stage. The brush up stage was especially tiring because it was an intricate process of comparing the effects of tiny differences. Finally, I submitted the necessary documents. It was an amazing experience to see my ideas take shape and exceed my expectations. I was able to rediscover the joy of ideation through this experience. Also, my efforts were happily paid off as I received the Special Award. (award from the judging committee)
I recommend this field to newcomers because good ideas can carry you far and there are supporting teachers at ICT. If you are interested, why not test your design skills here at ICT?
S2 Sagishima Yujin
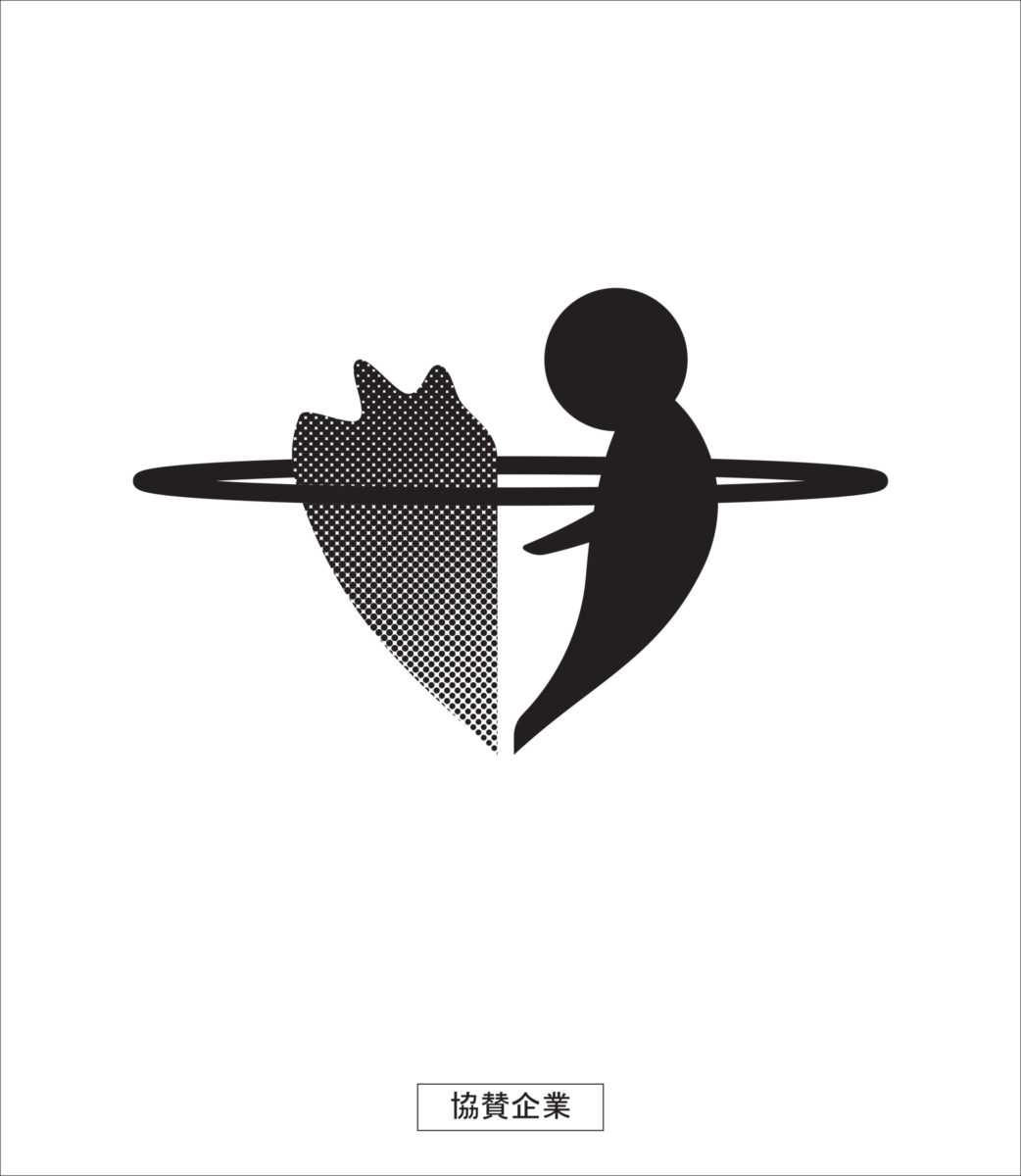
 皆さん、こんにちは。S科2年の鷺島です。今回は私が参加した、プロコンとロボコンに並ぶ高専三大コンテストの一つ、デザインコンペティション(以下デザコン)について書いていきます。
皆さん、こんにちは。S科2年の鷺島です。今回は私が参加した、プロコンとロボコンに並ぶ高専三大コンテストの一つ、デザインコンペティション(以下デザコン)について書いていきます。
デザコンは幾つかの区分に分かれていますが、私たち白山麓キャンパスの学生が参加できるのは、プレデザコン(高専1から3年生対象)となります。プレデザコンと言っても、分野が空間デザインフィールド(建築の透視図)、創造デザインフィールド(ロゴデザイン)、A Mデザインフィールド(3Dプリント)の3つに分かれており、それぞれの学生の得意分野で取り組むことができます。私自身は創造デザインフィールドを選択して今年の東京大会に参加しました。
今回のテーマは「名取市において、自然がもたらした試練を乗り越える力となった人と人とつながりを、次代へと継承してゆくこと」で、これを題材にしたロゴを作成しました。ここからは、簡単に何を経て完成へと至ったのか書いていきたいと思います。まず最初にしたのはテーマの咀嚼です。とくに今回のテーマは複雑で、最終的には「震災を乗り越えた人のつながりを示す」という一文に縮めました。次がアイデア出し、続いてブラッシュアップに入ります。ここが一番時間がかかる工程で、それぞれ1週間以上かかります。特にブラッシュアップに関しては、1つのロゴの些細な表現の差異を比べながら作業していくので、かなり疲れました。最後に提出資料にまとめれば完成です。どんどんアイデアが形になっていき、最終的に想像以上の作品が完成するのはとても壮観です。この活動を通して、アイデア創出の楽しさを再確認することができました。結果としては特別賞(審査委員会から頂ける賞)を獲得することができて嬉しく思います。
この分野は、アイデア勝負の部分も多く、サポートして頂ける先生たちも付いているので、初心者でも気軽に始められます。気になる人は是非最初の一歩を国際高専で踏み出してみてください。
S科2年 鷺島悠人
Hello everyone. My name is Sagishima and I am a second-year student of the department of science and technology. Today I would like to write about the Kosen Design Competition (DezaCon), which I participated in and is counted as one of the three big Kosen Contests along with the ProCon and RoboCon.
The DezaCon is divided into several divisions. The division that students from the Hakusanroku campus can participate in is the Pre-DezaCon (first- to third-year students). This Pre-DezaCon is further divided into three fields: the Space Design Field (architectural perspective drawing), Creative Design Field (logo design), and AM Design Field. (3D printing) Students can choose which fields they wish to compete in. I selected the Creative Design Field and entered this year's Tokyo tournament.
This year's theme was to create a logo based on the concept "Passing down the bond between people of Natori city who overcame the trial of nature." I would like to briefly describe how I reached my final product. First, I broke down the theme. This year's theme was complex, so I simplified it to the sentence "Display the bond between people who overcame the earthquake." Next, I brainstormed and began the brushing up process. These took the longest amount of time; about one week for each stage. The brush up stage was especially tiring because it was an intricate process of comparing the effects of tiny differences. Finally, I submitted the necessary documents. It was an amazing experience to see my ideas take shape and exceed my expectations. I was able to rediscover the joy of ideation through this experience. Also, my efforts were happily paid off as I received the Special Award. (award from the judging committee)
I recommend this field to newcomers because good ideas can carry you far and there are supporting teachers at ICT. If you are interested, why not test your design skills here at ICT?
S2 Sagishima Yujin
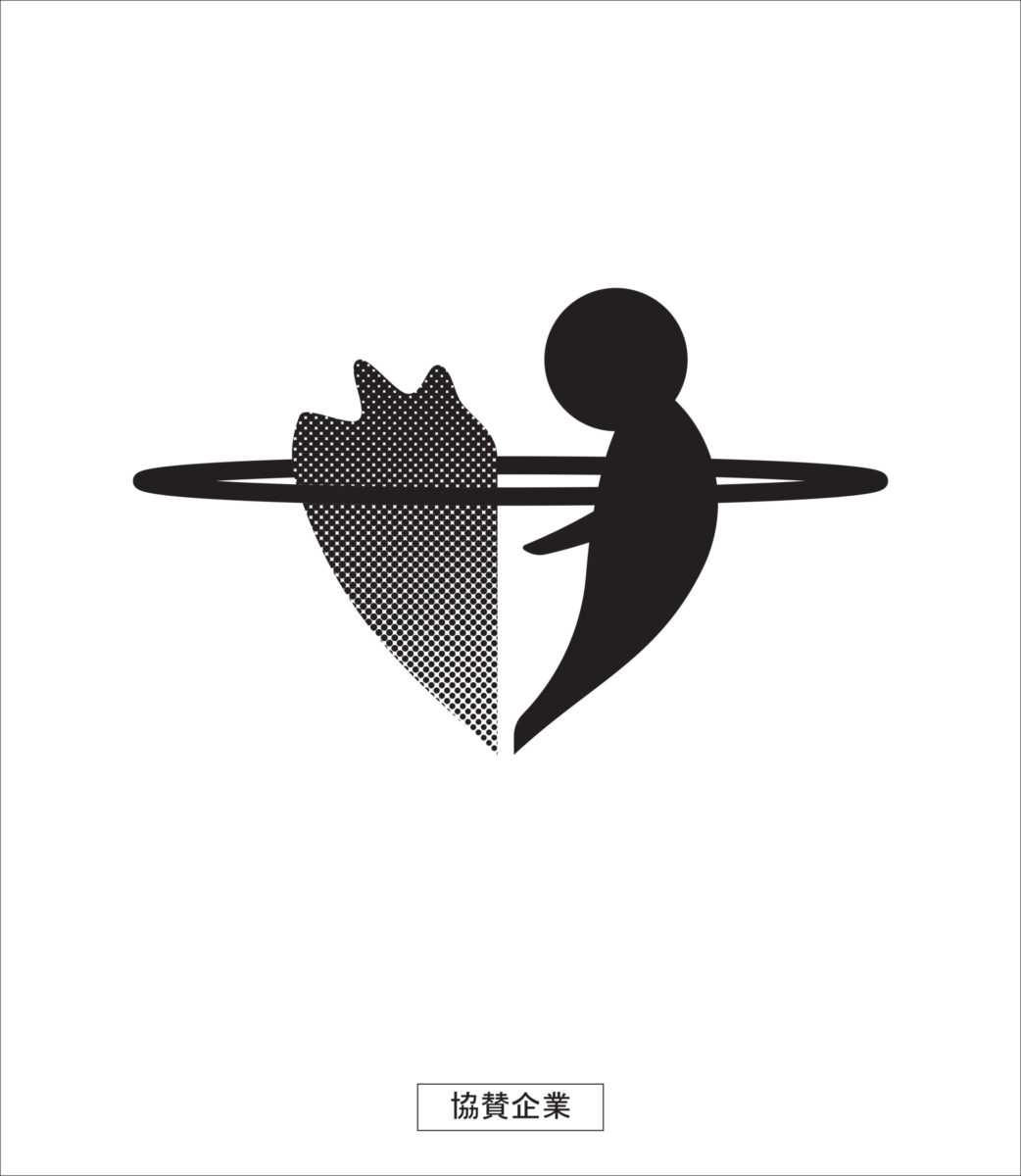
 こんにちは。1年生担任の木原です。今年も早いもので、あと残りわずかとなりました。学生のみんなが心待ちにしている冬休みが終わると、あと一か月ほどで授業が終了します。学生の皆さんはここでの寮生活の間、授業以外にも放課後の部活動や課外活動を通して様々な経験をしてきました。今日は2019年1年生にとっては最後の課外活動となった加賀友禅体験について紹介します。
こんにちは。1年生担任の木原です。今年も早いもので、あと残りわずかとなりました。学生のみんなが心待ちにしている冬休みが終わると、あと一か月ほどで授業が終了します。学生の皆さんはここでの寮生活の間、授業以外にも放課後の部活動や課外活動を通して様々な経験をしてきました。今日は2019年1年生にとっては最後の課外活動となった加賀友禅体験について紹介します。
本校では最先端の科学技術を学ぶだけではなく、古典的な芸能や美術にもふれあい、優れたイノベーターの育成を目指しています。その一環として本年度は9月24日に加賀友禅の工房久恒を工場見学させていただきました。そこでは加賀友禅が持つ優美な世界観や巧みな技法、また着物の伝統を守っていく大変さや新たな市場を開拓する工夫など、様々なお話をうかがいました。学生はその後、それぞれに感じたことや考えたこと、また伝統工芸が現在直面している問題に対する自分なりの解決策をまとめ、久恒さんにレポートを提出しています。
そして今回、12月21日に実際に加賀友禅の絵付けを体験させてもらいました。学生の皆さんはそれぞれが気に入った図柄に、思い思いの色で絵付けをしていました。同じ図柄を選んでも、学生によって全く違った色付けが生まれ、みんなの個性やセンスがよく表れた作品が完成しました。工学を学ぶ学校の中で、一生懸命真面目に美術に取り組んでいる1年生。担任としてみんなの将来がとても頼もしいと感じた時間でした。
Hello, this is Kihara, the first-year homeroom teacher. Time flies and this year is almost over. After the long awaited by students winter break, classes will finish in almost one month. Students have grown from their experience living here, not only through classwork, but also through club activities and extracurricular activities. In today's journal, I would like to talk about the first-year student's last event this year.
At ICT, we aim to foster exceptional innovators not only through high tech science and technology, but also through classical and traditional art. Following this objective, we visited the Kaga-yuzen Hisatsune Kobo workshop on September 24. There, we learned about the graceful world of Kaga-yuzen, its craftsmanship, the difficulty of protecting traditional kimonos, and the ingenuity put into cultivating a new audience. We also discussed possible solutions to the issues traditional art faces and presented them to Mr. Hisatsune.
On December 21, I finally had my chance to try Kaga-yuzen dyeing. Each student chose a picture of their liking and colored it. Even if the students chose the same picture, the finishing result was totally different depending on the colors and pattern they used. Each piece of work reflected their taste and personality well. We spend most of our time studying engineering here at ICT. Therefore, the pleasant sight of our first-year students engrossed in art gave me a feeling of confidence for their future.

 こんにちは。1年生担任の木原です。今年も早いもので、あと残りわずかとなりました。学生のみんなが心待ちにしている冬休みが終わると、あと一か月ほどで授業が終了します。学生の皆さんはここでの寮生活の間、授業以外にも放課後の部活動や課外活動を通して様々な経験をしてきました。今日は2019年1年生にとっては最後の課外活動となった加賀友禅体験について紹介します。
こんにちは。1年生担任の木原です。今年も早いもので、あと残りわずかとなりました。学生のみんなが心待ちにしている冬休みが終わると、あと一か月ほどで授業が終了します。学生の皆さんはここでの寮生活の間、授業以外にも放課後の部活動や課外活動を通して様々な経験をしてきました。今日は2019年1年生にとっては最後の課外活動となった加賀友禅体験について紹介します。
本校では最先端の科学技術を学ぶだけではなく、古典的な芸能や美術にもふれあい、優れたイノベーターの育成を目指しています。その一環として本年度は9月24日に加賀友禅の工房久恒を工場見学させていただきました。そこでは加賀友禅が持つ優美な世界観や巧みな技法、また着物の伝統を守っていく大変さや新たな市場を開拓する工夫など、様々なお話をうかがいました。学生はその後、それぞれに感じたことや考えたこと、また伝統工芸が現在直面している問題に対する自分なりの解決策をまとめ、久恒さんにレポートを提出しています。
そして今回、12月21日に実際に加賀友禅の絵付けを体験させてもらいました。学生の皆さんはそれぞれが気に入った図柄に、思い思いの色で絵付けをしていました。同じ図柄を選んでも、学生によって全く違った色付けが生まれ、みんなの個性やセンスがよく表れた作品が完成しました。工学を学ぶ学校の中で、一生懸命真面目に美術に取り組んでいる1年生。担任としてみんなの将来がとても頼もしいと感じた時間でした。
Hello, this is Kihara, the first-year homeroom teacher. Time flies and this year is almost over. After the long awaited by students winter break, classes will finish in almost one month. Students have grown from their experience living here, not only through classwork, but also through club activities and extracurricular activities. In today's journal, I would like to talk about the first-year student's last event this year.
At ICT, we aim to foster exceptional innovators not only through high tech science and technology, but also through classical and traditional art. Following this objective, we visited the Kaga-yuzen Hisatsune Kobo workshop on September 24. There, we learned about the graceful world of Kaga-yuzen, its craftsmanship, the difficulty of protecting traditional kimonos, and the ingenuity put into cultivating a new audience. We also discussed possible solutions to the issues traditional art faces and presented them to Mr. Hisatsune.
On December 21, I finally had my chance to try Kaga-yuzen dyeing. Each student chose a picture of their liking and colored it. Even if the students chose the same picture, the finishing result was totally different depending on the colors and pattern they used. Each piece of work reflected their taste and personality well. We spend most of our time studying engineering here at ICT. Therefore, the pleasant sight of our first-year students engrossed in art gave me a feeling of confidence for their future.

 S科1年ロボコンチームの畠中 義基です。
S科1年ロボコンチームの畠中 義基です。
2019年11月23日(土)に愛知県で行われた、第7回全国高校生コマ大戦 名古屋モーターショー場所に出場してきました。出場メンバーは、僕と、同じく国際理工学科1年の佐藤俊太朗と杉晃太朗の3人で1チームとして参加してきました。僕たちがコマの大会に出場することになったのは、9月の下旬に先生に勧められたことからでした。出場が決まってから約2か月間放課後にコマの製作と研究を何度も繰り返し約80個のコマを製作しました。最初のほうは、回転時間があまり伸びず嫌になることもありましたが、何とかやり遂げることができました。僕が最後までやり遂げることができたのは、同じデザイン&ファブリケーションクラブのプロコンチームが全国高等専門学校プログラミングコンテストで本選に出場するなど、結果を残している中で、ロボコンチームは、何も結果を残してないということに何か結果を出さないといけないと思っていたからです。大会の結果は予選敗退(7勝3敗)でした。負けた3試合は、すべて自分の失投(コマの投げミス)によるものだったのですごく悔しいです。もっと練習をしておけばよかったとすごく後悔しています。この負けを次のコマ大戦やほかの活動に活かしていきたいと思います。
畠中 義基
My name is Yoshiki Hatanaka. I'm a first year student of the Department of Science and Technology.
On November 23 (Sat), I participated in the 7th National High School Spintop Battle Tournament (Koma-taisen) at Nagoya Motor Show. Fellow first year students and teammates Shuntaro Sato and Koutaro Sugi also participated in this tournament. We learned about this tournament from our couch in the end of September. For two months after school, we manufactured and analyzed over 80 spintops. In the beginning, we could not improve our spining time and I felt like giving up at times. However, we stayed strong and pushed through to the end. The reason we were able to continue is because the ProCon team from the same Design and Fabrication Club participated in the National Kosen Programming Contest and we as a team felt pressure to achieve a result of our own. We were eliminated in the preliminary round with a record of seven wins and three losses. The three games we lost were due to a miss throw from myself, which was very frustrating. I regret that I didn't spend more time practicing spinning the tops. We plan to use this experience in future spintop tournaments and other activities.
Yoshiki Hatanaka
 S科1年ロボコンチームの畠中 義基です。
S科1年ロボコンチームの畠中 義基です。
2019年11月23日(土)に愛知県で行われた、第7回全国高校生コマ大戦 名古屋モーターショー場所に出場してきました。出場メンバーは、僕と、同じく国際理工学科1年の佐藤俊太朗と杉晃太朗の3人で1チームとして参加してきました。僕たちがコマの大会に出場することになったのは、9月の下旬に先生に勧められたことからでした。出場が決まってから約2か月間放課後にコマの製作と研究を何度も繰り返し約80個のコマを製作しました。最初のほうは、回転時間があまり伸びず嫌になることもありましたが、何とかやり遂げることができました。僕が最後までやり遂げることができたのは、同じデザイン&ファブリケーションクラブのプロコンチームが全国高等専門学校プログラミングコンテストで本選に出場するなど、結果を残している中で、ロボコンチームは、何も結果を残してないということに何か結果を出さないといけないと思っていたからです。大会の結果は予選敗退(7勝3敗)でした。負けた3試合は、すべて自分の失投(コマの投げミス)によるものだったのですごく悔しいです。もっと練習をしておけばよかったとすごく後悔しています。この負けを次のコマ大戦やほかの活動に活かしていきたいと思います。
畠中 義基
My name is Yoshiki Hatanaka. I'm a first year student of the Department of Science and Technology.
On November 23 (Sat), I participated in the 7th National High School Spintop Battle Tournament (Koma-taisen) at Nagoya Motor Show. Fellow first year students and teammates Shuntaro Sato and Koutaro Sugi also participated in this tournament. We learned about this tournament from our couch in the end of September. For two months after school, we manufactured and analyzed over 80 spintops. In the beginning, we could not improve our spining time and I felt like giving up at times. However, we stayed strong and pushed through to the end. The reason we were able to continue is because the ProCon team from the same Design and Fabrication Club participated in the National Kosen Programming Contest and we as a team felt pressure to achieve a result of our own. We were eliminated in the preliminary round with a record of seven wins and three losses. The three games we lost were due to a miss throw from myself, which was very frustrating. I regret that I didn't spend more time practicing spinning the tops. We plan to use this experience in future spintop tournaments and other activities.
Yoshiki Hatanaka
 Hello, it's Jonathan, the camera man. On October 21, a group of students from the Hakusanroku campus climbed Mt. San-po-iwa-take. (三方岩岳) Sanpoiwatake is a mountain on the Hakusan-Shirakawago White Road. The White Road runs from Hakusanroku to Shirakawago in Gifu prefecture and is a popular tourist spot, especially in the autumn. The leaves were beautiful shades of red, yellow and green as we made our way up the path. This event was a collaboration with the Oguchi Community Center and some members of the local community joined us in the climb. Shinichi Hiramatsu is a specialist of this area and gave lectures about trees and animals. It took about an hour to reach the top, where we rested and ate lunch. Hiramatsu-san pointed out that we could see Mt. Hakusan's peak from Sanpoiwatake. Altogether, it was a refreshing and fun way to spend a beautiful autumn day.
Hello, it's Jonathan, the camera man. On October 21, a group of students from the Hakusanroku campus climbed Mt. San-po-iwa-take. (三方岩岳) Sanpoiwatake is a mountain on the Hakusan-Shirakawago White Road. The White Road runs from Hakusanroku to Shirakawago in Gifu prefecture and is a popular tourist spot, especially in the autumn. The leaves were beautiful shades of red, yellow and green as we made our way up the path. This event was a collaboration with the Oguchi Community Center and some members of the local community joined us in the climb. Shinichi Hiramatsu is a specialist of this area and gave lectures about trees and animals. It took about an hour to reach the top, where we rested and ate lunch. Hiramatsu-san pointed out that we could see Mt. Hakusan's peak from Sanpoiwatake. Altogether, it was a refreshing and fun way to spend a beautiful autumn day.
Jonathan
こんにちは、ジョナサンです。10月21日(月)、白山麓キャンパスの学生と一緒に白山白川郷ホワイトロードにある三方岩岳(さんぽういわたけ)を登りました。ホワイトロードは石川県と岐阜県を結ぶ有料道路で、人気の観光名所です。特に紅葉の季節にたくさんの方が訪れます。三方岩岳の登山口はホワイトロードの途中にあります。この日は美しい赤、黄色、緑の景色の中、登山を楽しむことができました。今回の登山は尾口公民館と合同で行われ、現地のメンバーも同行しました。白山の自然に詳しい平松新一さんも同行者のひとりで、歩きながら学生に動植物のレクチャーをしていました。1時間ほどで頂上に到着し、そこで昼食を食べました。三方岩岳からは白山の頂上、御前峰を望むことができ、美しい景色を見てリフレッシュできる日となりました。
ジョナサン
-

登山口はホワイトロードの岐阜川にあります
-

紅葉に包まれて登りました
-

三方岩岳 頂上にて
-

頂上で昼食を食べました
-

解説する平松新一さん
-

三方岩岳から望む白山
 Hello, it's Jonathan, the camera man. On October 21, a group of students from the Hakusanroku campus climbed Mt. San-po-iwa-take. (三方岩岳) Sanpoiwatake is a mountain on the Hakusan-Shirakawago White Road. The White Road runs from Hakusanroku to Shirakawago in Gifu prefecture and is a popular tourist spot, especially in the autumn. The leaves were beautiful shades of red, yellow and green as we made our way up the path. This event was a collaboration with the Oguchi Community Center and some members of the local community joined us in the climb. Shinichi Hiramatsu is a specialist of this area and gave lectures about trees and animals. It took about an hour to reach the top, where we rested and ate lunch. Hiramatsu-san pointed out that we could see Mt. Hakusan's peak from Sanpoiwatake. Altogether, it was a refreshing and fun way to spend a beautiful autumn day.
Hello, it's Jonathan, the camera man. On October 21, a group of students from the Hakusanroku campus climbed Mt. San-po-iwa-take. (三方岩岳) Sanpoiwatake is a mountain on the Hakusan-Shirakawago White Road. The White Road runs from Hakusanroku to Shirakawago in Gifu prefecture and is a popular tourist spot, especially in the autumn. The leaves were beautiful shades of red, yellow and green as we made our way up the path. This event was a collaboration with the Oguchi Community Center and some members of the local community joined us in the climb. Shinichi Hiramatsu is a specialist of this area and gave lectures about trees and animals. It took about an hour to reach the top, where we rested and ate lunch. Hiramatsu-san pointed out that we could see Mt. Hakusan's peak from Sanpoiwatake. Altogether, it was a refreshing and fun way to spend a beautiful autumn day.
Jonathan
こんにちは、ジョナサンです。10月21日(月)、白山麓キャンパスの学生と一緒に白山白川郷ホワイトロードにある三方岩岳(さんぽういわたけ)を登りました。ホワイトロードは石川県と岐阜県を結ぶ有料道路で、人気の観光名所です。特に紅葉の季節にたくさんの方が訪れます。三方岩岳の登山口はホワイトロードの途中にあります。この日は美しい赤、黄色、緑の景色の中、登山を楽しむことができました。今回の登山は尾口公民館と合同で行われ、現地のメンバーも同行しました。白山の自然に詳しい平松新一さんも同行者のひとりで、歩きながら学生に動植物のレクチャーをしていました。1時間ほどで頂上に到着し、そこで昼食を食べました。三方岩岳からは白山の頂上、御前峰を望むことができ、美しい景色を見てリフレッシュできる日となりました。
ジョナサン
-

登山口はホワイトロードの岐阜川にあります
-

紅葉に包まれて登りました
-

三方岩岳 頂上にて
-

頂上で昼食を食べました
-

解説する平松新一さん
-

三方岩岳から望む白山


































